びわの葉でなぜ癌や難病が治るのか② 家庭での使い方

びわの葉を使った治療法の中では温灸療法が最も有名ですが、その他にも葉や種を家庭でできるいろんな使い方がありますのでご紹介します。
SPONSORED LINK
マッサージ
びわの葉を火であぶって使う方法があります。
これは昭和初期の頃、静岡県の金地院という禅寺のお坊さんが行っていた方法で、なんでも医者から見放された難病の人たちを20万人も救ったと言われています。
やり方は簡単で次のように行います。
①びわの葉を2枚用意します。
②光沢のあるほうをガスレンジなどの火を使って焦げないように炙ります。

ご覧になればおわかりのように、下の葉が光沢のあるほうです。
③2枚の葉の光沢のある方を合わせて10回ほどすり合わせます。
④熱いうちに皮膚に当てて押し込むようになでる。
これだけです。
この方法は金地院療法とも呼ばれますが、この治療で治ったのはびわの葉の効能に加えて、お寺の禅師に特別な力があったからだとも言われています。
その伝説的エピソードを一つご紹介しますとある少女が結核による腹膜炎で腹部が硬く膨れ上がっていました。
それが、たった5分のびわの葉治療で綿のように柔らかくなったそうです。
この金地院療法は医師である福島博士(札幌鉄道病院物理科長)が調査を行った結果、「効果は迅速で確実性があり、万病に効く」と報告されています。
遠赤外線の治療器
棒もぐさの代わりに電気熱を使います。
治療器の先端にびわの葉かびわの種子のエキスを浸み込ませて皮膚に遠赤外線を照射して、体内に薬効を浸透させる方法です。
効果的には自然の熱である棒もぐさのほうがよいようです。
葉と種からエキスを取り出す方法
びわの葉か種を焼酎に3カ月弱漬けこむことでびわのエキスが溶け込みます。
このエキスは外傷や火傷、腰痛や肩こり、皮膚病などに効果があり、湿布にすれば病気による痛みを緩和することができます。
また、湿布はびわの葉を直接体に当てて行うことでも、痛みの緩和には効果があります。
びわの葉ではなく、種を玄米焼酎に漬けることでもびわのエキスを得ることができます。
Sponsored Link
お茶
びわの葉を細かく切って、それを煎じてお茶として飲むこともできます。
びわ茶を飲むと体が温まり、利尿効果があるのでお小水がよく出ます。 腎臓が弱く排尿が良くない方やむくみ易い方にはお勧めです。 慢性胃炎や咳止めにも効果があります。
少し香ばしい香りがし、味はほうじ茶とウーロン茶の間くらいの味でしょうか。私は好きでよく飲んでいます。
ねじめびわ茶 【楽天】
余談ですが、江戸時代にはびわ茶にシナモンやその他の生薬を加えた甘い飲み物が、夏バテに効く飲み物として流行ったそうです。
同じく夏バテと言えば、びわの葉の黒焼きも夏バテ回復の特効薬になります。
また、びわの葉をお風呂に入れれば皮膚病によいでしょう。 体が芯から温まりますので硬くなった筋肉をほぐしてくれます。
種を食べる
びわの有効成分アミダクリンは強い抗ガン作用があることがわかっていますが、これはびわの葉よりも種のほうが1000倍~2000倍のアミダクリンを含んでいます。
これを毎日、1個か2個食べるだけでもアミダクリンをはじめとしたびわの薬効を取り入れることができます。
実際、末期癌の人が1日2個ずつ食べていたら癌が1ヵ月で消えたそうです。
種が硬い人はすりおろしてから食べるとよいでしょう。
びわの種は塩漬けにすれば長期にわたって保存することもできます。
こんにゃくパスター
びわの葉を体に当てて、葉の上に温めたこんにゃくを乗せる療法があります。
これはびわの葉の薬効を温めたこんにゃくの温熱刺激によって体内に浸透させることができ、こんにゃくの特殊な酵素がそれをさらに促進させます。
また、びわの葉をおろして、それに生姜汁と小麦を合わせて練ったパスターを作り、それを患部に当てるという使い方もあります。
ここでご紹介してきたびわを使った治療法は下記の本に詳しいやり方が載っていますので、やってみたい方はご覧になられるとよいでしょう。
参考文献 「ビワの葉 自然療法」 望月研
また、全国各地にびわを普及している組織や施術を受けられる所がありますので「びわの葉温灸 地名」で検索されると探すことができると思います。
Sponsored Link
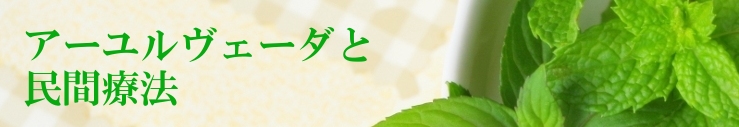















この記事へのコメントはありません。